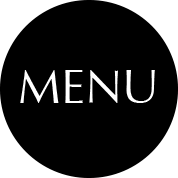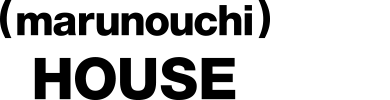Text_Viola Kimura
今回のゲストは、知的に障がいのあるアーティストが集う「アトリエ インカーブ」代表の今中博之氏。14年前にアトリエを立ち上げて以来、在籍アーティストの作品を国内外の美術館やギャラリーへ発信している。自身も、100万人に1人の確率で発症する「偽性アコンドロプラージア(先天性両下肢障がい)」と向き合う。社会福祉法人の経営企画、空間設計を手がけるほか、企業や自治体のプロジェクトに参画し、ソーシャルデザインに関わる提案に携わる。福祉の世界のオピニオンリーダーだ。現在は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の一員としても活躍している。 2010年に開催した丸の内ハウスでのエキシビションでは、「感激のあとに、“居心地の良さ”のような余韻が続く」という声を残したが、その背景にはどのような思想と積み重ねがあるのだろうか。彼の、あらゆる個性を持つ人々の表現の捉え方とはどのようなものなのか。また、4年後のオリンピック開催に向け動くなかで、日本社会をどのように捉えているのか…。リオ五輪目前のいま、丸の内ハウスへ再来した彼に、話を聞いた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
![]()
アトリエインカーブはどのような経緯で始まったのでしょうか。
丸の内ハウスでもエキシビションをされていましたね。
「2002年に開業した社会福祉法人です。僕はもともと空間系のデザイン会社で働いていました。20年近く仕事をしましたが、僕自身の障がいが進行するのと同時に、デザインの「独創性」や「オリジナリティ」というところに意識が向き始めるタイミングが訪れます。ある知的障がいのあるアーティストに出会い、彼らの作品に触れて、ぞくっと心が揺らいだんです。それでサラリーマンを辞め、アトリエインカーブを立ち上げることに。社会福祉法人を設立するために、行政との事務手続きに相当の時間を要して、全て準備を済ませるのに5年ほどかかりました。アーティストは前職時代からのご縁で集まった方が大半で、現在26名が在籍しています。丸の内ハウスでは、そのうち2人のアーティストにフィーチャーした展示をやらせていただきました。
アトリエ インカーブは、国内外でのエキシビションのほかに、作品自体の販売とグッズの販売を行っています。作品が売れた際の売上げは、必要経費を除いて100%アーティストのもとへ入ります。作品の販売場所は、アートフェア東京を除き、いまは海外が多いです。国内ではアート作品の市場が小さいためです。ニューヨークとシンガポールのアートフェアに出展したのですが、一度ですぐに結果を出すのは難しくて、粘りづよく出展してようやく売上げが立ってくるという具合でやっています。」
「独創性」について詳しく聞かせてください。
そこへの気付きというのは、何がきっかけだったんでしょうか。
「僕がやっていた「デザイン」は、美術史やデザイン史といった「教育」を受けた上で成り立たせることができる、言わばコピー&ペーストの世界でした。100年前のものと60年前のものと、現在のものをコラージュしてものを形作っていくというやり方に終始する。そんなことを20年近くやったのですが、知的障がいを持つアーティストに出会ったときに、そうした模倣が全くない、オリジナルの作品性に初めて触れて。それは、誰かの目を気にして作られるものではなく、我がためだけに作られたものでした。他者にはないものを作る、評価を求めない人たちという存在が、率直にかっこいいと思ったんです。」
アトリエ インカーブを立ち上げる前に海外の国々を回っていたとのことですが、どんなご体験を。
「一年間休職して行きました。旅の目的のひとつは、「“オリジナル”とはどういうことか知りたかった」ということです。まず、昔から好きだったコルビュジェという建築家の作品を見るために、アメリカ西海岸、東海岸、フランス、スイスを巡りました。しかし、実際に見てみると、大して面白さを感じなかったんです。その理由は、彼の建築物も作為的なものだったからなのでしょう。「この位置に立ったら綺麗に見える」とか「この廊下を抜けたときにこういう照明が入ったら美しいだろう」ということが計算し尽くされていた。
旅の途中で、フランスのとある郵便局員が建てたお墓「シュバルの理想宮」に遭遇しました。彼は建築家でもデザイナーでもないんですが、パリ万博のころに郵便配達をしていた際に、その配達する絵はがきの絵柄を見ながら石を拾い集め、自分と奥さんが入るお墓を建ててしまった。そのお墓を実際に目の当たりにしたとき、全く作為的ではない、自分と彼女のためだけに作ったからこその美しさに感銘を受けました。「これが“オリジナル”なのだ」、と。
その経験から、「アート」はオリジナル性を追求すべきもので、「デザイン」はオリジナル性を追求すべきではないもの。と、自分のなかで切り分けができました。その後日本に帰ってきて、僕の友人のデザイナーが連れてきたアーティストに出会ってアトリエ インカーブの活動を始めることになります。」